財務・税務
医療機関のコスト管理について考える
医療機関のガバナンスを考える
あすの監査法人 公認会計士 山岡 輝之
多くの医療機関では3月を決算期とすることから、この記事を読まれているころには年度決算数値が確定しているのではないかと思います。令和6年度の医療機関の決算状況は、前年度以前より業績が悪化している法人が増えているのではないでしょうか。このほど全国公私病院連盟が公表した 「令和6年病院運営実態分析調査の概要」 では、赤字病院数の割合は回答した病院の80.1%となり、前年比で3.2ポイント上昇しました。この結果からも、現在の病院経営はさらに厳しい状況に向かっていることがわかります。特に人件費や経費、委託費が大幅に増加し、収益が増収となってもそれだけでは費用の増加分を吸収しきれない状況です。
近年では物価高騰や賃金の上昇圧力など、外部環境を要因とするコストが増えています。一方、病院の収入の大半は公定価格の保険診療収入であるため、コスト増加分を価格に転嫁できないことが医療機関にとってはジレンマとなっています。むやみにコスト削減を進めることは、かえって医療従事者のモチベーションや医療の質の低下を招き、結果としてさらなる病院経営のマイナスとなる悪循環を引き起こしかねません。そのため、医療機関のコスト管理は大胆に進めたい一方、慎重さも大切になります。
しかしながら、医療機関の経営者・医療従事者・職員全てに言えることかもしれませんが、もう少し自らの医療機関の持続的な運営を実現するために、コスト管理に対してシビアに向き合ってもいいのではないかと感じることがあります。今回は、私見ではありますが、医療機関のコスト管理でもう少し意識してもらいたい3点について考えてみたいと思います。
近年では物価高騰や賃金の上昇圧力など、外部環境を要因とするコストが増えています。一方、病院の収入の大半は公定価格の保険診療収入であるため、コスト増加分を価格に転嫁できないことが医療機関にとってはジレンマとなっています。むやみにコスト削減を進めることは、かえって医療従事者のモチベーションや医療の質の低下を招き、結果としてさらなる病院経営のマイナスとなる悪循環を引き起こしかねません。そのため、医療機関のコスト管理は大胆に進めたい一方、慎重さも大切になります。
しかしながら、医療機関の経営者・医療従事者・職員全てに言えることかもしれませんが、もう少し自らの医療機関の持続的な運営を実現するために、コスト管理に対してシビアに向き合ってもいいのではないかと感じることがあります。今回は、私見ではありますが、医療機関のコスト管理でもう少し意識してもらいたい3点について考えてみたいと思います。
➀システム導入・保守管理に関するコスト管理について
医療機関を取り巻く環境としては、医療ICTの利活用やサイバーセキュリティへの対策等も不可欠であり、システム関連の投資額は年々増加していると思います。電子カルテシステムの導入・更新で10億を超える投資予算を目にする機会も出てきました。
これらの投資額を診療報酬で賄うことは相当な負担となり、当然に医療機関内部でも慎重に検討していると思います。しかし、その導入過程を確認すると、疑問に感じることがあります。とある医療法人の理事会議事録を確認したところ、電子カルテのメーカーを先に決定している事例がありました。メーカーを決めたあとで金額や仕様内容を詰めていくという導入の流れが予定されていました。この導入スタイルでは、ベンダーの提案を鵜呑みにせざるを得ない、金額の交渉を優位に進められない、もっと既製品で安く済ませられる選択肢があるかもしれないのにその選択肢が取れないといった問題が残ってしまうのではないでしょうか。
そもそも、大学医局との兼ね合いでメーカーは所与とするというようなことも耳にしますが、財政状況等を考慮していない選択は、経営の持続可能性を無視した意思決定になっていないかと疑ってしまいます。まずはノンカスタマイズを前提に、自院の課題解決に最適な製品がどれであるかを調査し、現場の業務負担や人的負担の軽減に貢献できるかというような視点も加味して判断すべきではないでしょうか。
これらの投資額を診療報酬で賄うことは相当な負担となり、当然に医療機関内部でも慎重に検討していると思います。しかし、その導入過程を確認すると、疑問に感じることがあります。とある医療法人の理事会議事録を確認したところ、電子カルテのメーカーを先に決定している事例がありました。メーカーを決めたあとで金額や仕様内容を詰めていくという導入の流れが予定されていました。この導入スタイルでは、ベンダーの提案を鵜呑みにせざるを得ない、金額の交渉を優位に進められない、もっと既製品で安く済ませられる選択肢があるかもしれないのにその選択肢が取れないといった問題が残ってしまうのではないでしょうか。
そもそも、大学医局との兼ね合いでメーカーは所与とするというようなことも耳にしますが、財政状況等を考慮していない選択は、経営の持続可能性を無視した意思決定になっていないかと疑ってしまいます。まずはノンカスタマイズを前提に、自院の課題解決に最適な製品がどれであるかを調査し、現場の業務負担や人的負担の軽減に貢献できるかというような視点も加味して判断すべきではないでしょうか。
➁人材派遣料・紹介料の支払いについて
人件費・経費の増加の中で、人材派遣料と紹介料が伸びていることをよく目にします。診療報酬が医療従事者の配置を基準としていることから、医療機関としてはどんな手を使ってでも人材の確保が最優先とされるのかもしれません。看護師で言えば、日本看護協会から公表された 「2024年病院看護実態調査」 の結果では、2023年度の離職率は正規雇用の看護職員は11.3%と前年度比0.5ポイント減となったものの、10人に1人以上は離職する職場となっています。同レベルで看護師の確保をしなければならないのは医療機関にとって辛いところです。
人材派遣料・紹介料の支払いが経費増となり、医療機関にとってかなりの負担になっているのも事実です。この状況が医療機関の内部において十分に理解されていないのではないかと思うこともあります。職員の採用と定着を安定化させることは、病院運営の持続可能性を高めることにも寄与することを皆が理解する必要があると考えます。
人材派遣料・紹介料の支払いが経費増となり、医療機関にとってかなりの負担になっているのも事実です。この状況が医療機関の内部において十分に理解されていないのではないかと思うこともあります。職員の採用と定着を安定化させることは、病院運営の持続可能性を高めることにも寄与することを皆が理解する必要があると考えます。
➂コスト管理に対するチェック機能が働いていない
医療機関ではさまざまな観点からコスト管理が求められていますが、例えば、物品の購入や契約などにおいて、十分に内部での検討が行われているのか、経営者だけでなく、内部相互間でもチェックが十分に働いていないのではないかと感じることがあります。予算内に収まったからそれ以上の検討はしない、他部署の契約には口出ししないと決めてしまい、横串でチェックするような牽制が図れていないのではと思うことがあります。もちろん、経営者や事務局長が中心となってチェック機能を働かせる必要があると思いますが、例えば内部監査や監事が業務監査の一環として経営的な視点から監査することも考えられます。
苦しい時こそ、誰かだけの問題ではなく働く職場全員の問題として、持続可能な運営を実現するためのコスト管理はどのようにすべきか、考えてみてはいかがでしょうか。
【2025. 6. 1 Vol.3 メディカル・マネジメント】
苦しい時こそ、誰かだけの問題ではなく働く職場全員の問題として、持続可能な運営を実現するためのコスト管理はどのようにすべきか、考えてみてはいかがでしょうか。
【2025. 6. 1 Vol.3 メディカル・マネジメント】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20
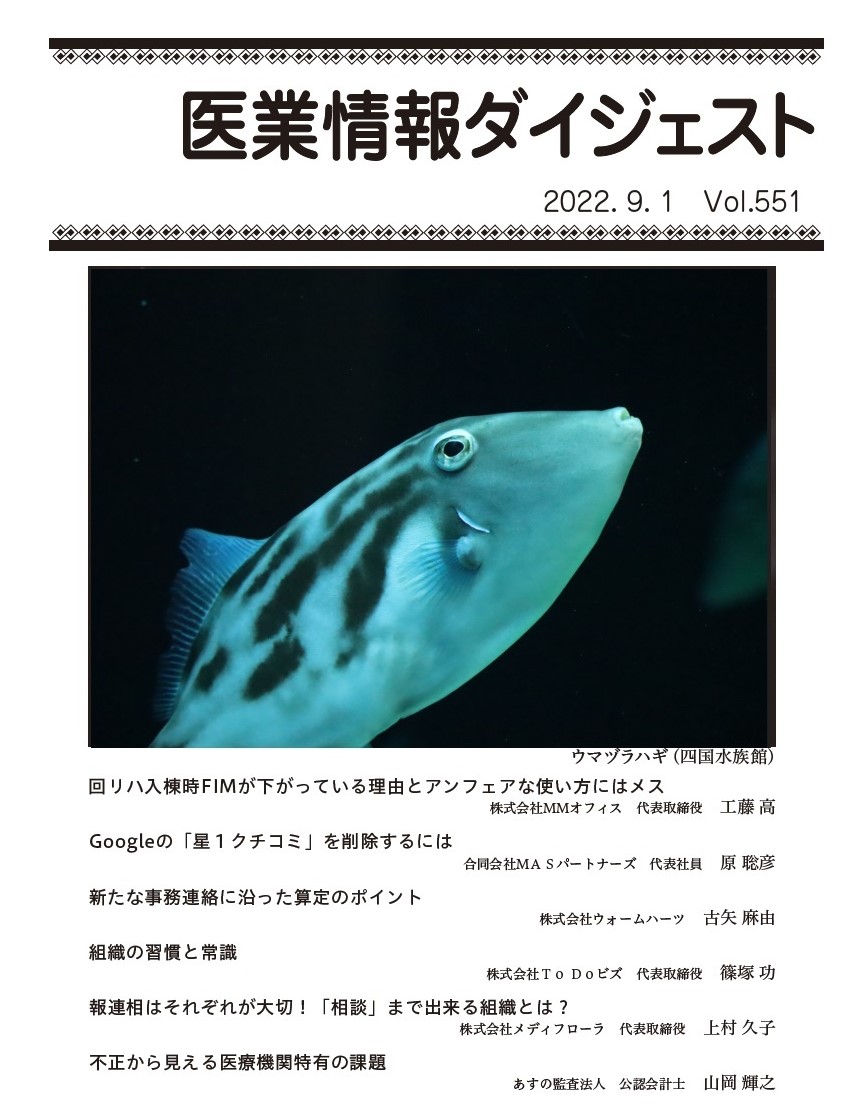
2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
2025-12-23
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-01-16現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2026-01-16
骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~
2026-01-15
地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-
2026-01-15
【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略
2026-01-14
敷地内薬局の評価の在り方の検討
2026-01-13
財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し
2026-01-09
現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記
2026-01-09
短期的に効率を重視するか、中長期的に個人が成長する環境をつくるか
2026-01-09
長時間労働の是正と時間外労働の事前申請
2026-01-09
患者に “選ばれるクリニック” はこうつくる!
2026-01-08
「療養・就労両立支援指導料」について運用の留意点
2026-01-07
中山間・人口減少地域での新しい特例介護サービス案
2026-01-06
精神病床から介護医療院の道を整備すべき

