財務・税務
医療機関の購買モラルについて考える
医療機関のガバナンスを考える
あすの監査法人 公認会計士 山岡 輝之
最近、長野県の公立病院に勤務する医師が、医療 機器を優先的に使う見返りにメーカーから現金を受 け取り、収賄の罪で起訴されました。報道記事をご 覧になった方も多いと思います。
この事例では、医療機器を優先的に使う見返りと して、機器を使用することにより貯まるポイント数 に応じ、私的な領収書と引き換えに現金の受け渡し が行われていたとされています。
そもそも、医療機器を医師が自ら選び、さらには 発注まで行っていたとされており、公立病院でそこ までできてしまう体制となっていたことにも驚きま した。
さらに調べてみますと、2024年には、特定の医療 機器メーカーのインプラントを病院内で優先的に使 用する見返りとして、公的病院の医師が現金を複数 回にわたり受け取った収賄の容疑で逮捕されたとい う記事もありました。
なぜ、今回私がこの話題を取り上げたかというと、 クライアント先である病院の事務局が医師から以下 のような相談を受け、それを私に相談してきたこと がきっかけでした。
この事例では、医療機器を優先的に使う見返りと して、機器を使用することにより貯まるポイント数 に応じ、私的な領収書と引き換えに現金の受け渡し が行われていたとされています。
そもそも、医療機器を医師が自ら選び、さらには 発注まで行っていたとされており、公立病院でそこ までできてしまう体制となっていたことにも驚きま した。
さらに調べてみますと、2024年には、特定の医療 機器メーカーのインプラントを病院内で優先的に使 用する見返りとして、公的病院の医師が現金を複数 回にわたり受け取った収賄の容疑で逮捕されたとい う記事もありました。
なぜ、今回私がこの話題を取り上げたかというと、 クライアント先である病院の事務局が医師から以下 のような相談を受け、それを私に相談してきたこと がきっかけでした。
【相談内容】
業者から手術で使用する特定の診療材料について、年間で一定額を超えて使用した場合、年度末にその超えた額について支払額の割引を受ける提案を受けている。
医師としては、自らの診療科のモチベーションアップに繋がるので、その割引分を自らの診療科の研究研修費として割り当ててほしいという要望があった。この要望を受け入れることに問題はないか。
もし、自分がこのような相談を医師から持ち掛けられたら、どのように回答しますか?
まず、費用の観点から見れば、材料費の費用削減に貢献する話であったとしても、結果として特定の診療科の研究研修費として使用する限り、病院の利益貢献には何ら繋がりません。
また、研究研修費の枠が増えることを期待して、本来の目的以上に特定の診療材料を使用したとすれば、そもそも費用削減になるのか、また、診療を受ける側の患者にとっても最適な診療を行っているかは疑わしく、倫理的な側面から見ても問題が残ってしまうのではないでしょうか。
材料費の削減効果を原価計算等で診療科の利益貢献に反映し、その成果を成果給として給与賞与に反映するということであれば、正当な評価と言えるのかもしれませんが、今回の質問は、一歩間違えればコンプライアンス問題に発展しかねない内容であったと言えます。
今回は、メーカーの提案を受けた医師から事務局に相談があったためにわかりましたが、もしも医師とメーカー担当者だけで勝手に進められ、割引分を個人の利得にしてしまった場合には新聞の一面に掲載されてしまうような問題に発展したでしょう。
医療機器や診療材料、医薬品などは専門性や実際の使い勝手の問題もあり、医師やコメディカルなどの専門職がメーカーと交渉を進めざるを得ないとは思います。しかし、選定あるいは発注までも現場の職員任せにしてしまうと、やはりその先に癒着や不公正な取引の問題が生じてしまいがちです。医療機関の経営は厳しく、管理機能を充実させるにも一定の限界はありますが、その中でこのような問題を少しでも防ぐためには、私見ですが以下の取組みが重要となってくると思います。
医師としては、自らの診療科のモチベーションアップに繋がるので、その割引分を自らの診療科の研究研修費として割り当ててほしいという要望があった。この要望を受け入れることに問題はないか。
もし、自分がこのような相談を医師から持ち掛けられたら、どのように回答しますか?
まず、費用の観点から見れば、材料費の費用削減に貢献する話であったとしても、結果として特定の診療科の研究研修費として使用する限り、病院の利益貢献には何ら繋がりません。
また、研究研修費の枠が増えることを期待して、本来の目的以上に特定の診療材料を使用したとすれば、そもそも費用削減になるのか、また、診療を受ける側の患者にとっても最適な診療を行っているかは疑わしく、倫理的な側面から見ても問題が残ってしまうのではないでしょうか。
材料費の削減効果を原価計算等で診療科の利益貢献に反映し、その成果を成果給として給与賞与に反映するということであれば、正当な評価と言えるのかもしれませんが、今回の質問は、一歩間違えればコンプライアンス問題に発展しかねない内容であったと言えます。
今回は、メーカーの提案を受けた医師から事務局に相談があったためにわかりましたが、もしも医師とメーカー担当者だけで勝手に進められ、割引分を個人の利得にしてしまった場合には新聞の一面に掲載されてしまうような問題に発展したでしょう。
医療機器や診療材料、医薬品などは専門性や実際の使い勝手の問題もあり、医師やコメディカルなどの専門職がメーカーと交渉を進めざるを得ないとは思います。しかし、選定あるいは発注までも現場の職員任せにしてしまうと、やはりその先に癒着や不公正な取引の問題が生じてしまいがちです。医療機関の経営は厳しく、管理機能を充実させるにも一定の限界はありますが、その中でこのような問題を少しでも防ぐためには、私見ですが以下の取組みが重要となってくると思います。
➀ 交渉を現場任せにしない
長野県の公立病院の事例では、医療機器の選定や発注を医師が行っていたとされていますが、医療機器や材料費、委託契約などさまざまな取引について、現場の専門職に一任するのではなく、購買部門の職員なども十分に関与し、業者選定や取引条件の決定、契約手続まで進めることが肝要です。
➁院内各種委員会の権限と機能を十分に発揮させる
病院内では医療機器であれば選定委員会、診療材料等の材料であれば購買委員会等が開催され、新規購入や契約条件等について検討が進められると思います。これらの委員会で十分な議論を行い、不正の兆候や不当な条件などコンプライアンスの観点から問題ない取引となっているか目を光らせ、監視する役割をもっと発揮していくことが必要になると思います。議事録を見ていても、採用品目の紹介のような委員会となっており、委員会自体が形骸化しているように受け取れるケースもあります。改めて、病院にとって、患者にとって望ましい取引となっているか牽制する役割を各種委員会に期待したいところです。
➂コンプライアンスの必要性を理解する
医療機関の購買業務は、取引額も大きく、専門性も高くなり、各診療科やコメディカルがメーカーと直接交渉を進めることも多いため、贈収賄をはじめとする不正リスクが高くなる傾向にあります。特に各部署の責任者には、改めてコンプライアンスの意識を高めるとともに、思わぬところでコンプライアンス違反に抵触することを未然に防止するためにも、研修等を通してコンプライアンス遵守の必要性を改めて理解する機会を定期的に設けることも大切です。
【2025年9月1日号 Vol.9 メディカル・マネジメント】
【2025年9月1日号 Vol.9 メディカル・マネジメント】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20
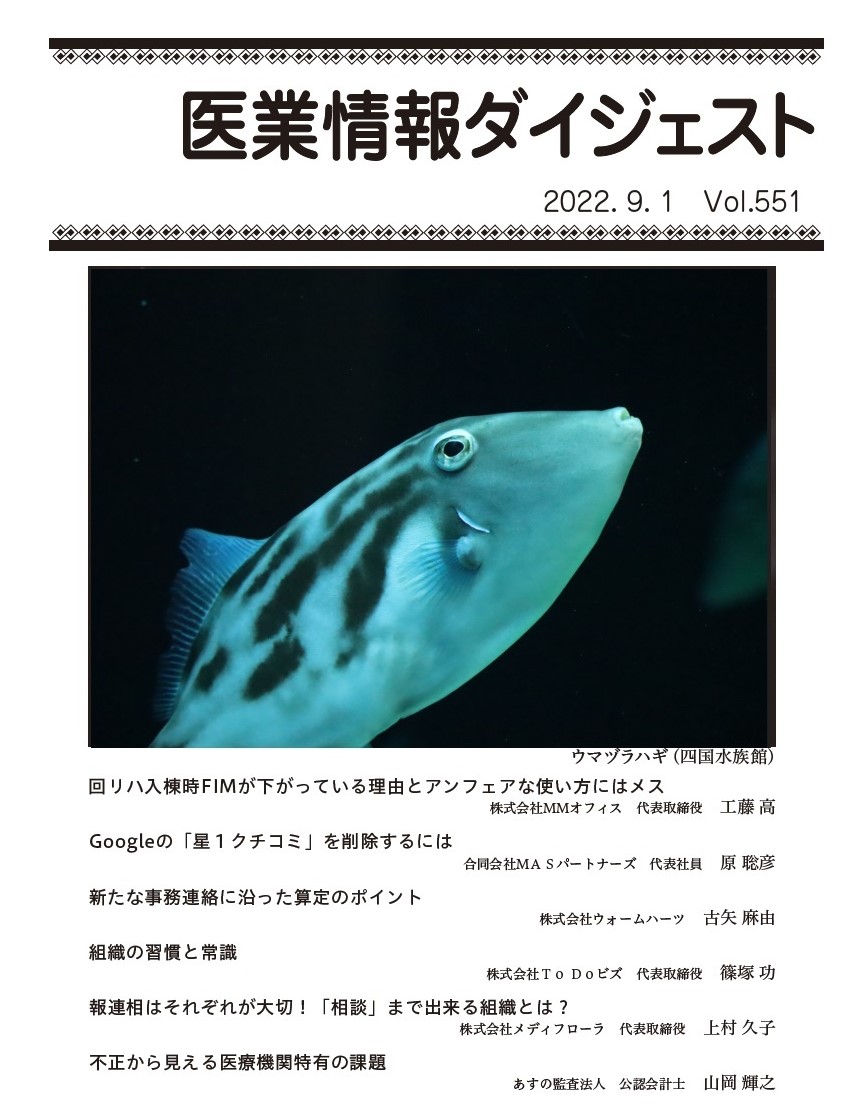
2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略
2026-01-14
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”
2026-02-24
新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む
2026-02-20
新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資
2026-02-20
元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―
2026-02-20
在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察
2026-02-18
病院職員の退職給付制度について考える(1)
2026-02-16
現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2026-02-11
外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―
2026-02-10
薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―
2026-02-09
最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金
2026-02-06
薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討
2026-02-05
話しがズレていく…

