組織・人材育成
「毎日感謝を伝え合おう!」ルールになった組織の話
組織力が高まるケーススタディ
株式会社メディフローラ 代表取締役 上村 久子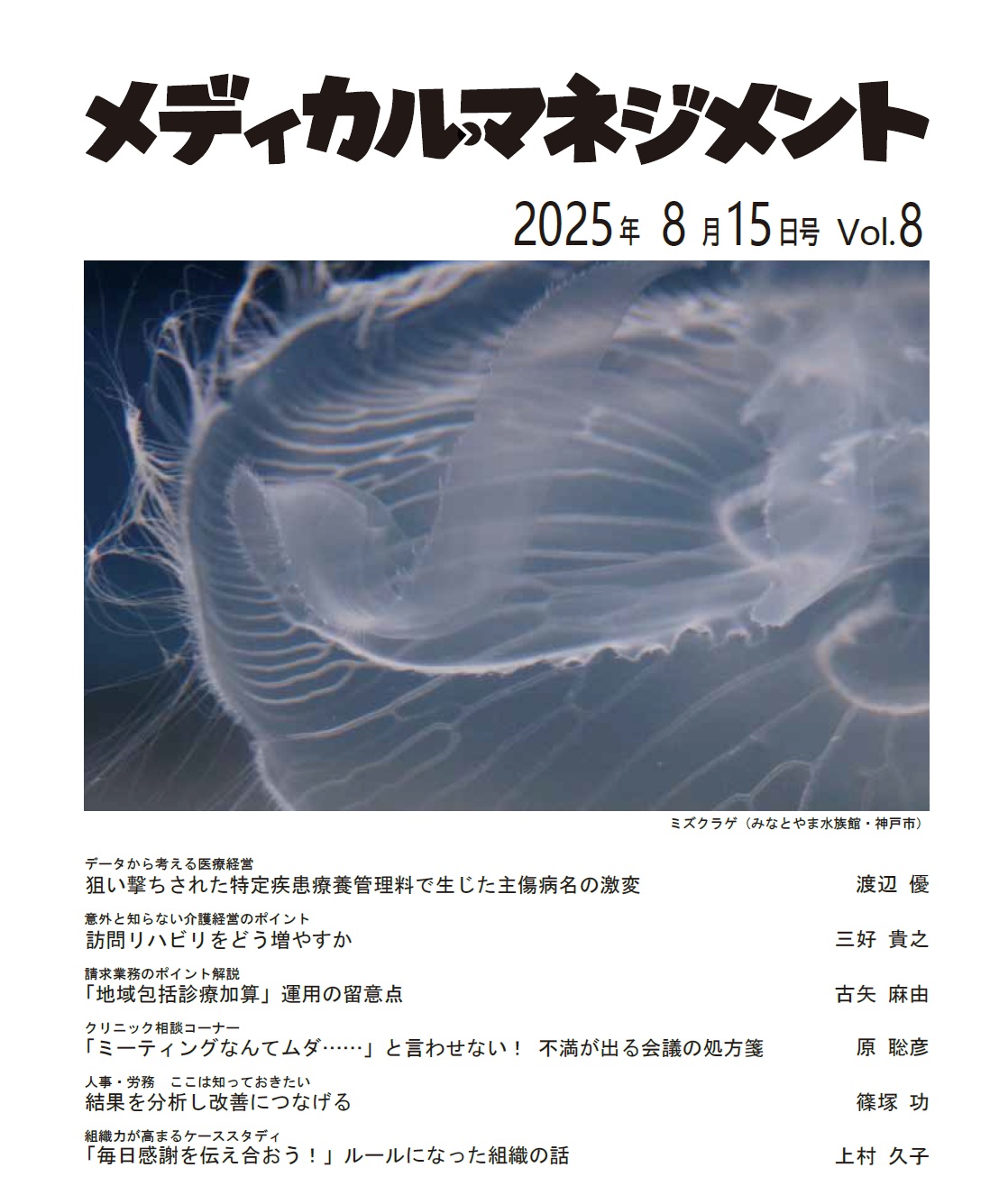
毎日忙しい業務の中で心身が疲弊し、殺伐とした雰囲気になり、思いやりの言葉が少なくなってしまうことはよくあります。忙しい職場だからこそ意識的により良い組織を作る環境を作り上げたい――と、サンキューカードなど、 「感謝が溢れる雰囲気づくり」 に挑戦している組織は珍しくありません。その結果、上手くいく組織もあれば、想像していた成果が上がらない組織もあるようです。
今回は、 「感謝を伝え合う」 ことをルール化した組織の事例から、狙い通りの効果を組織に与えるための考え方について学んでいきたいと思います。
今回は、 「感謝を伝え合う」 ことをルール化した組織の事例から、狙い通りの効果を組織に与えるための考え方について学んでいきたいと思います。
ケース
海産物が特産品である地域にあるクリニックのお話です。このクリニックの院長先生は悩んでいました。
院長先生 「忙しい中で職員は頑張っている。だが、うちの職員は自己肯定感の低い若者が多く、忙しいだけの職場では心身ともに疲弊していくだけではないか。職員にとって癒しとなる活動を行っていこう!」
そこで院長先生は 「毎日、お昼のミーティングで職員同士感謝を伝え合おう!」 とルールを決めたのでした。
職員同士で具体的に感謝を伝え合うためには、お互いの動きを見ていなければなりません。とある職員は、この取り組みによって一緒に働く職員の動きをよく見るようになり、そこで初めて気が付く色々な職員の心配りが学びになり、感動したと言います。しかし、この取り組みについて、そのような肯定的な意見ばかりではな ようです。
職員A 「毎日毎日、何かしらの感謝を具体的に言わなければならなくて、正直疲れてしまいました。他のみんなもそんな感じだと思いますよ。毎日何か出来事が起こるわけでもありませんし、言うことがなくなってきてしまって……お昼のミーティングの時間が微妙な雰囲気になっている気がします」
職員B 「確かに、お互いの動きに気を配るようになったことは良いと思うんです。でも、仕事中、私たちは職員同士で自然に感謝の言葉を言い合っているんです。だからこの取り組みについて話が出た時に 『院長先生は私たちがお互いに感謝を伝え合っていないと思っているのだ』 と穿った見方をしてしまいました。院長先生に直接確認したわけではないのですが、院長先生がそう思っていたならば残念です」
職員C 「もう1か月このルールが続いています。院長先生がこのミーティングに参加していたのは最初の3日くらいで、あとは 『院長である私がいたら言いにくいだろうから』 と職員だけで行っています。院長先生が参加していないのに取り組みの効果なんて分かるのでしょうか…」
職員からの厳しい声は院長先生には届かず、職員のモヤモヤとした日は続いています。
このケース、どのような感想を持ちましたか?組織の中で新しい取り組みに挑戦する際には、良い点だけではなく、気を付けなければならない点も出てくるものです。今回のケースの場合、組織の雰囲気をより良くしたいという目的自体は決して悪いものではないはずです。しかし、現場で働いている職員にとって、目的としている成果が本当に得られるかどうかは、目的の良し悪しとは別の問題です。
なぜこのような問題が発生してしまったのか、考えていきましょう。私は、大きく分けて3点あると思います。
1点目は、 「院長先生が想像している組織の課題と、実行された取り組みの繋がりが分かりにくい点」 です。職員が疲弊しているという問題に対して、解決策は 「感謝を伝え合うこと」 であるとは限らないはずですが、院長先生の中では 「こうに違いない」 と思い込んでしまっているようです。第三者として聞くとおかしなことに気が付くと思いますが、意外にも 「最適な解決策だと思い込んでしまう」 ことは少なくないように感じます。
2点目は 「課題の当事者である職員の声を聞いていない(聞いているつもりになっている)点」 です。職員のために行われる組織開発の取り組みのはずが、職員は不在のまま企画され、実行されるケースもよくある話です。良いと信じて実行しているリーダーに対してものを申すことができる環境にない職員も多いことから、リーダー自ら職員に対して 「このような企画を考えているが、率直にどう考えるか?」 と、耳を傾ける努力があったほうが、狙った目的は達成しやすいと思います。
最後に3点目は 「取り組みの効果をリーダーと職員が一体となって見直し、改善する体制が整っていない点」 です。1点目で指摘した通り、最適な解決策であると信じ込んでしまうことは少なくないようで、取り組みに対する効果測定ができないまま何となく継続し、最終的には結果が出ないで取り組み自体が尻つぼみになってしまうケースは珍しくありません。組織は進化する生き物ですので、組織活性化の取り組みはその組織の開発段階に沿って進化すべきです。そのための検証は、組織一体となって見直すことが重要です。どのような点が良かったのか、どうすればもっと良かったのか、冷静に話し合い改善していくからこそ、組織は学び、磨かれていきます。
組織をより良く活性化させるための取り組みは、この3点に注意して挑戦されることをお勧めいたします。
【2025年8月15日号 Vol.8 メディカル・マネジメント】
院長先生 「忙しい中で職員は頑張っている。だが、うちの職員は自己肯定感の低い若者が多く、忙しいだけの職場では心身ともに疲弊していくだけではないか。職員にとって癒しとなる活動を行っていこう!」
そこで院長先生は 「毎日、お昼のミーティングで職員同士感謝を伝え合おう!」 とルールを決めたのでした。
職員同士で具体的に感謝を伝え合うためには、お互いの動きを見ていなければなりません。とある職員は、この取り組みによって一緒に働く職員の動きをよく見るようになり、そこで初めて気が付く色々な職員の心配りが学びになり、感動したと言います。しかし、この取り組みについて、そのような肯定的な意見ばかりではな ようです。
職員A 「毎日毎日、何かしらの感謝を具体的に言わなければならなくて、正直疲れてしまいました。他のみんなもそんな感じだと思いますよ。毎日何か出来事が起こるわけでもありませんし、言うことがなくなってきてしまって……お昼のミーティングの時間が微妙な雰囲気になっている気がします」
職員B 「確かに、お互いの動きに気を配るようになったことは良いと思うんです。でも、仕事中、私たちは職員同士で自然に感謝の言葉を言い合っているんです。だからこの取り組みについて話が出た時に 『院長先生は私たちがお互いに感謝を伝え合っていないと思っているのだ』 と穿った見方をしてしまいました。院長先生に直接確認したわけではないのですが、院長先生がそう思っていたならば残念です」
職員C 「もう1か月このルールが続いています。院長先生がこのミーティングに参加していたのは最初の3日くらいで、あとは 『院長である私がいたら言いにくいだろうから』 と職員だけで行っています。院長先生が参加していないのに取り組みの効果なんて分かるのでしょうか…」
職員からの厳しい声は院長先生には届かず、職員のモヤモヤとした日は続いています。
このケース、どのような感想を持ちましたか?組織の中で新しい取り組みに挑戦する際には、良い点だけではなく、気を付けなければならない点も出てくるものです。今回のケースの場合、組織の雰囲気をより良くしたいという目的自体は決して悪いものではないはずです。しかし、現場で働いている職員にとって、目的としている成果が本当に得られるかどうかは、目的の良し悪しとは別の問題です。
なぜこのような問題が発生してしまったのか、考えていきましょう。私は、大きく分けて3点あると思います。
1点目は、 「院長先生が想像している組織の課題と、実行された取り組みの繋がりが分かりにくい点」 です。職員が疲弊しているという問題に対して、解決策は 「感謝を伝え合うこと」 であるとは限らないはずですが、院長先生の中では 「こうに違いない」 と思い込んでしまっているようです。第三者として聞くとおかしなことに気が付くと思いますが、意外にも 「最適な解決策だと思い込んでしまう」 ことは少なくないように感じます。
2点目は 「課題の当事者である職員の声を聞いていない(聞いているつもりになっている)点」 です。職員のために行われる組織開発の取り組みのはずが、職員は不在のまま企画され、実行されるケースもよくある話です。良いと信じて実行しているリーダーに対してものを申すことができる環境にない職員も多いことから、リーダー自ら職員に対して 「このような企画を考えているが、率直にどう考えるか?」 と、耳を傾ける努力があったほうが、狙った目的は達成しやすいと思います。
最後に3点目は 「取り組みの効果をリーダーと職員が一体となって見直し、改善する体制が整っていない点」 です。1点目で指摘した通り、最適な解決策であると信じ込んでしまうことは少なくないようで、取り組みに対する効果測定ができないまま何となく継続し、最終的には結果が出ないで取り組み自体が尻つぼみになってしまうケースは珍しくありません。組織は進化する生き物ですので、組織活性化の取り組みはその組織の開発段階に沿って進化すべきです。そのための検証は、組織一体となって見直すことが重要です。どのような点が良かったのか、どうすればもっと良かったのか、冷静に話し合い改善していくからこそ、組織は学び、磨かれていきます。
組織をより良く活性化させるための取り組みは、この3点に注意して挑戦されることをお勧めいたします。
【2025年8月15日号 Vol.8 メディカル・マネジメント】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略
2026-01-14
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”
2026-02-24
新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む
2026-02-20
新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資
2026-02-20
元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―
2026-02-20
在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察
2026-02-18
病院職員の退職給付制度について考える(1)
2026-02-16
現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2026-02-11
外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―
2026-02-10
薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―
2026-02-09
最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金
2026-02-06
薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討
2026-02-05
話しがズレていく…

