病院・診療所
病床過剰地域での 有床診療所の開設・増床は可能か?
クリニック相談コーナー
合同会社MASパートナーズ 代表社員 原 聡彦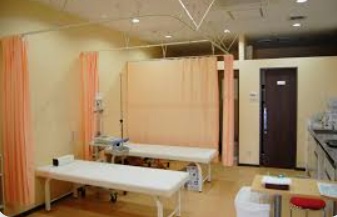
【相談実例】
これまでの臨床経験を活かして、短期入院手術、在宅医療の受け皿機能としての有床診療所で新規開業したいと考えていたところ、知人が開設している一人医師医療法人の有床診療所(5床。現在は病床稼働していない)を継承のお話を頂きました。病床を10床に増床して事業継承をする計画で動いておりましたが、管轄の保健所から病床過剰地域における増床は難しいと指摘がありました。有床診療所であれば増床はできるとコンサルタントからもアドバイスを受けていたので大船に乗った気分でおりましたが、途方にくれています。なんとか10床の有床診療所で継承開業をしたいのですが…」というご相談を頂きました。
【回 答】
医療法改正により平成19年1月1日から有床診療所の一般病床の設置または増床は都道府県の許可を受けなければならなくなりました。特に病床過剰地域での有床診療所の一般病床の設置及び増床は許可を得ることが非常に難しくなっています。しかし、ご相談のように「在宅医療の受け皿機能を有する」ということであれば、手続きを踏めば10床の有床診療所での継承開業は可能です。
今回は有床診療所の開設及び増床をご検討されている先生方に病床の設置等に係る手続き方法についてお伝えします。
今回は有床診療所の開設及び増床をご検討されている先生方に病床の設置等に係る手続き方法についてお伝えします。
1.許可を受けないで一般病床を設置(増床)する
都道府県によって違いはありますが、病床を管轄する担当行政官庁に事前相談が必要です。必ず事前相談を行ってから計画を推進することをお勧めします。
今回は相談のあった医療圏の事例をご紹介いたします。ご相談の診療所が所在する都道府県においては診療所の一般病床の設置または増床を行う場合、厚生労働省令で定める場合を除いて、都道府県知事の許可を要し、あわせて基準病床数による制限を受けています。特に病床過剰圏域となっている医療圏域では原則、診療所の一般病床の設置または増床を行うことはできないということになっています。一方、今後、高齢化の進行等に伴い、医療・介護の需要が増加し、多様化することが見込まれる中で、地域医療に重要な役割を果たしている有床診療所の設置を促進しています。
法律的には医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づき、許可を受けないで有床診療所の開設及び増床することが可能となります。許可を受けずに一般病床の設置又は増床ができる診療所の類型は下記のとおりです。
■許可を受けないで一般病床の設置又は増床ができる診療所の類型
第1号 居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所
第2号 へき地に設置される診療所
第3号 小児医療、周産期医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要であると認められる診療所
一般病床の設置または増床を希望する場合は上記の第1号~第3号に該当する診療所の類型の機能を有することが必要です。「在宅医療の受け皿機能」は第1号の類型に当てはまりますので、増床のできる診療所の類型に当てはまります。
今回は相談のあった医療圏の事例をご紹介いたします。ご相談の診療所が所在する都道府県においては診療所の一般病床の設置または増床を行う場合、厚生労働省令で定める場合を除いて、都道府県知事の許可を要し、あわせて基準病床数による制限を受けています。特に病床過剰圏域となっている医療圏域では原則、診療所の一般病床の設置または増床を行うことはできないということになっています。一方、今後、高齢化の進行等に伴い、医療・介護の需要が増加し、多様化することが見込まれる中で、地域医療に重要な役割を果たしている有床診療所の設置を促進しています。
法律的には医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づき、許可を受けないで有床診療所の開設及び増床することが可能となります。許可を受けずに一般病床の設置又は増床ができる診療所の類型は下記のとおりです。
■許可を受けないで一般病床の設置又は増床ができる診療所の類型
第1号 居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所
第2号 へき地に設置される診療所
第3号 小児医療、周産期医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要であると認められる診療所
一般病床の設置または増床を希望する場合は上記の第1号~第3号に該当する診療所の類型の機能を有することが必要です。「在宅医療の受け皿機能」は第1号の類型に当てはまりますので、増床のできる診療所の類型に当てはまります。
2.病床の設置又は増床する場合の手続き方法
上記1に該当し病床の設置等を希望する診療所は、各行政官庁等に意見を得た上で都道府県の医療審議会において審議を行うことになっています。法律的には許可を受けないで一般病床を設置(増床)できるものの、実務上は地区医師会、医療圏域の専門部会、都道府県医療審議会へ了承を得る必要があるので実際は許可と同じぐらいの内容となります。
<実際の手続きの流れ>
事前相談(管轄の保健所、地区医師会、都道府県庁医務課に事前相談)→計画など指定の書類を提出→分科会に出席してプレゼン→医療審議会用資料提出→都道府県医療審議会の決議→保健医療計画に記載された有床診療所——という流れになります。
<実際の手続きの流れ>
事前相談(管轄の保健所、地区医師会、都道府県庁医務課に事前相談)→計画など指定の書類を提出→分科会に出席してプレゼン→医療審議会用資料提出→都道府県医療審議会の決議→保健医療計画に記載された有床診療所——という流れになります。
3. 長期戦を覚悟して具体的な計画を書面で丁寧に事前相談を行うこと
弊社がサポートしたケースでは診療所が病床過剰地域にあったため、地区医師会、各行政官庁へ事前相談を丁寧に行いました。事前相談を行う際のポイントは、具体的な計画(資金計画、収支計画、図面、開設時期等)を書面などで「見える化」して示すことです。審議会などで使用する定型の様式を行政官庁で準備しているケースが多いので、事前にホームページの様式集を確認するか、担当官から入手して計画を記載して頂くことをお勧めします。
また、医療圏を管轄する市町村の方針もあるため、「許可を受けないで病床を増床ができる」というところまでに1年以上の時間を要するケースがあります。長期戦を覚悟して先生の想いを地区医師会、市町村、圏域の医療審議会へプレゼンテーションして頂くことをお勧めします。
【2022. 6. 1 Vol.545 医業情報ダイジェスト】
また、医療圏を管轄する市町村の方針もあるため、「許可を受けないで病床を増床ができる」というところまでに1年以上の時間を要するケースがあります。長期戦を覚悟して先生の想いを地区医師会、市町村、圏域の医療審議会へプレゼンテーションして頂くことをお勧めします。
【2022. 6. 1 Vol.545 医業情報ダイジェスト】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[新着記事]
2025-12-12生成AIとの付き合い方
2025-12-12
現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2025-12-11
リテンションとしての新たなポジションの創設
2025-12-10
組織文化と価値観のすり合わせ
2025-12-09
「掃除=雑務」の誤解を解く! 院長が取り組むべき職場風土づくり
2025-12-08
薬局に内部留保を残す理由とは
2025-12-05
治験等の研究研修費の取扱いについて考える
2025-12-05
2040年を見据えた在宅療養支援診療所薬剤師の役割と展望
2025-12-04
現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記
2025-12-03
【若手薬剤師もわかる】薬局のチーム力を高めるリーダーシップ入門(第1回)
2025-12-02
「遠隔画像診断による画像診断管理加算」 のメリットと算定状況は?
2025-12-01
今後の在宅医療の重要性
2025-11-28
まだまだ急性期365日リハビリは少ない

