病院・診療所
誤って過払いになっている通勤手当は返還を求めることができるのか?
手当の支給をルール化する
合同会社MASパートナーズ 代表社員 原 聡彦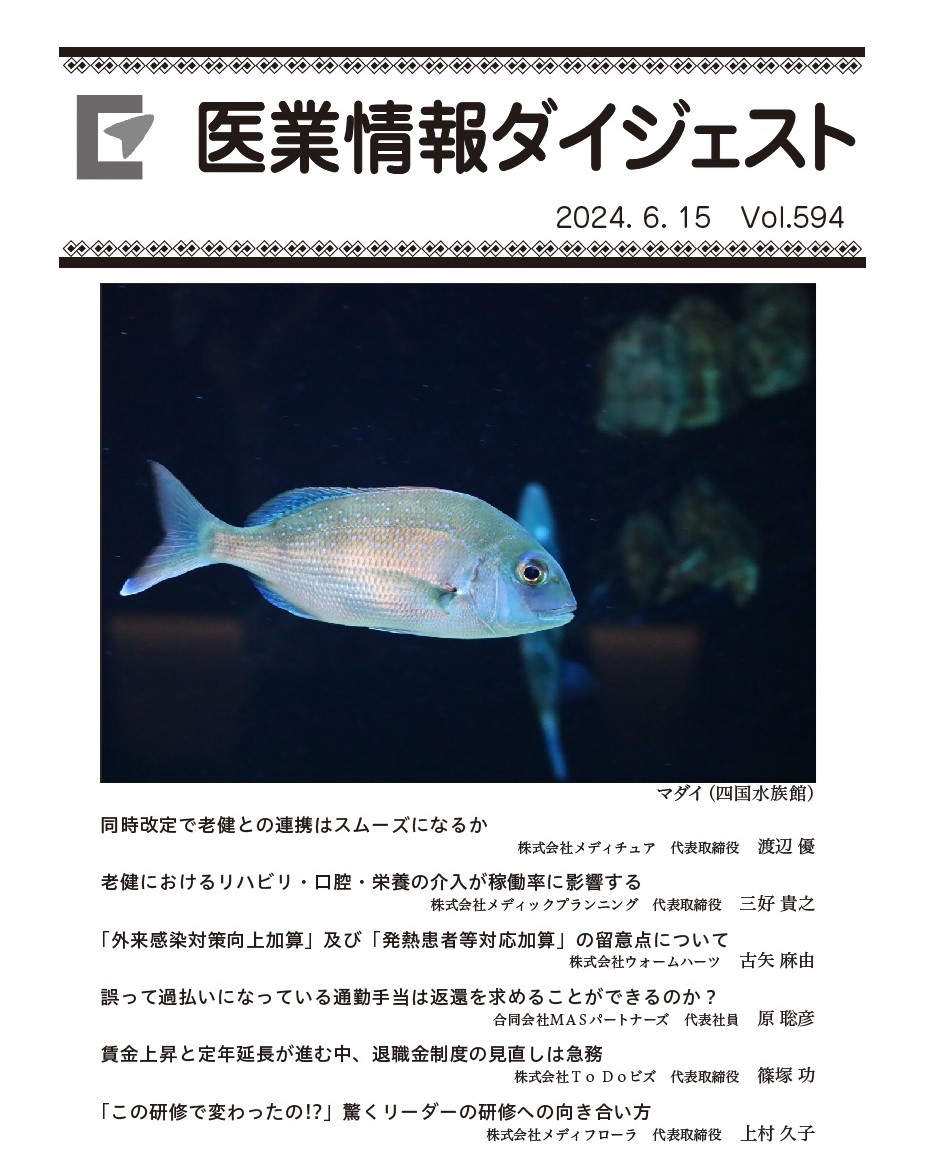
【相談内容】
近畿地方の開業10年目の整形外科クリニックの院長より「先日、あるスタッフに支払っていた通勤手当が、引越しをしていたにもかかわらずクリニックの確認ミスにより2年にわたって多く支払い過ぎであったことが判明しました。金額としては約10万円程度過払いになっています。ダメ元で過払い分の返還を求めたいのですが問題ないでしょうか。また、返還を求めるに際し、返還額が多額となることからトラブルにつながるのは避けたいと考えています。どのように対応したらよいのでしょうか?」という相談がありました。
【回 答】
「ダメ元で」言うなら後々問題になる可能性がありますのでやめたほうがよろしいかと思います。通勤手当などの過払い分の給与は、返金の義務が法律的にあることを理論武装して予め手順を考えていただくことをお勧めします。
手順として、まずは給与計算を誤ったお詫びをしたうえで、そのスタッフには過払い分を返還する義務がある旨を伝えましょう。
民法第703条により、事業主側(クリニック側)には不当利得返還請求権があるため、過払い分の返還請求が可能です。その際、返還しやすい方法をスタッフと相談して、生活をおびやかさないよう、本人の支払いやすい方法にすることが大切です。
なお、労働基準法第24条によって、「賃金の全額支払い」の定めがあることから、原則的に給与から天引きをする相殺の方法は認められていません。
また、給与の過払いに対する返還請求の時効は、原則として支払い時から10年ですが、発覚してからできるだけ早く手続きを行うことが重要です。
スタッフへ丁寧に説明する手順を考えるうえで、下記の点を踏まえて検討していただくことをお勧めします。
手順として、まずは給与計算を誤ったお詫びをしたうえで、そのスタッフには過払い分を返還する義務がある旨を伝えましょう。
民法第703条により、事業主側(クリニック側)には不当利得返還請求権があるため、過払い分の返還請求が可能です。その際、返還しやすい方法をスタッフと相談して、生活をおびやかさないよう、本人の支払いやすい方法にすることが大切です。
なお、労働基準法第24条によって、「賃金の全額支払い」の定めがあることから、原則的に給与から天引きをする相殺の方法は認められていません。
また、給与の過払いに対する返還請求の時効は、原則として支払い時から10年ですが、発覚してからできるだけ早く手続きを行うことが重要です。
スタッフへ丁寧に説明する手順を考えるうえで、下記の点を踏まえて検討していただくことをお勧めします。
1. 給与計算の誤り及び支払い過ぎとなっている給与の取り扱いは?
給与計算においてはミスのない確実な計算と支払いが求められますが、現実的には計算や支払ミスが頻繁に発生しますし、ミスが起きやすいポイントが複数存在します。今回のケースのような通勤手当をはじめとする諸手当の変更は、ミスがおきやすい代表的な項目に挙げられるでしょう。こうした不当に多く支払い過ぎた給与の取り扱いについては、民法第703条に「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」と規定されています。
つまり、スタッフが不当に利益を得て、その一方でクリニックが損をしている(不当利得)とき、スタッフはクリニックに対してその相当分について返還義務があるということです。その義務は原則10年間消滅しないと定められています。
つまり、スタッフが不当に利益を得て、その一方でクリニックが損をしている(不当利得)とき、スタッフはクリニックに対してその相当分について返還義務があるということです。その義務は原則10年間消滅しないと定められています。
2.返還が生じるようになった場合は?
法律で返還義務があるといっても返還するように求められたスタッフは、必ずしも快く応じるとは限りません。場合によっては不信感を募らせ、退職してしまう可能性もありますので、クリニックはミスを認め謝罪し、すべての期間ではなく例えば1年間のみとするなど、減額措置を検討することも必要と思います。
また、多額の返還を一括で求めることはスタッフに大きな負担となり、生活に支障をきたす可能性があります。そのため分割により複数月にわたって返還するなど、その返還方法についてはスタッフと相談して決めることが望まれます。
また、多額の返還を一括で求めることはスタッフに大きな負担となり、生活に支障をきたす可能性があります。そのため分割により複数月にわたって返還するなど、その返還方法についてはスタッフと相談して決めることが望まれます。
3. 手当の支給のルール化~スタッフ自身に管理することを促す~
通勤手当の誤り支給が発生してしまう要因には、スタッフの連絡忘れなどのクリニックに責任がない場合も多くありますが、申し出のルールがはっきりしておらず、結果的にクリニックが管理しなければならない状態であることが多くみられます。このような状況で誤って手当を支給すると、クリニックに落ち度があるためスタッフに過支給していた期間の全額を返還するように求めづらくなります。このような状況にならないよう、クリニックとスタッフが相互確認できる仕組みを導入することをお勧めします。例えば、賃金の諸手当の支給について賃金規程等で細かくルール化して、入職時や変更時にコンサルタントや社労士など専門家に説明をしてもらっているクリニックもあります。届出が遅れた場合、「手当支給の変更や要件に外れる事由が発生しているにもかかわらず届出が遅れた場合はその事実が発生した月に遡って手当の返還義務が生じる」とスタッフにペナルティーが生じることをあらかじめ説明しておけば、スタッフが自分自身で管理するよう心掛けるようになってきます。
ぜひ専門家と相談しながら自主管理を促すルールを作り、そのルールをスタッフへ浸透させることをお勧めします。
【2024. 6. 15 Vol.594 医業情報ダイジェスト】
ぜひ専門家と相談しながら自主管理を促すルールを作り、そのルールをスタッフへ浸透させることをお勧めします。
【2024. 6. 15 Vol.594 医業情報ダイジェスト】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略
2026-01-14
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-02-09最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金
2026-02-06
薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討
2026-02-05
話しがズレていく…
2026-02-03
現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記
2026-02-02
最低賃金の上昇と医療機関のパートタイム・有期雇用職員の賃金制度
2026-01-30
「勝手な残業」に悩む院長へ ―黙示の指示を生まない残業ルールのつくり方―
2026-01-30
年末年始における 「休日加算」 について運用の留意点
2026-01-29
介護施設の生産性向上は実現可能か
2026-01-28
最低賃金アップで経営悪化は不可抗力
2026-01-27
現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記
2026-01-26
【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略
2026-01-26
ちゃんと覚えないと大変なことになるのに!

