組織・人材育成
なぜ組織で仕事をしているのか ~組織の5原則~
医療機関のリーダーの気付き
株式会社メディフローラ 代表取締役 上村 久子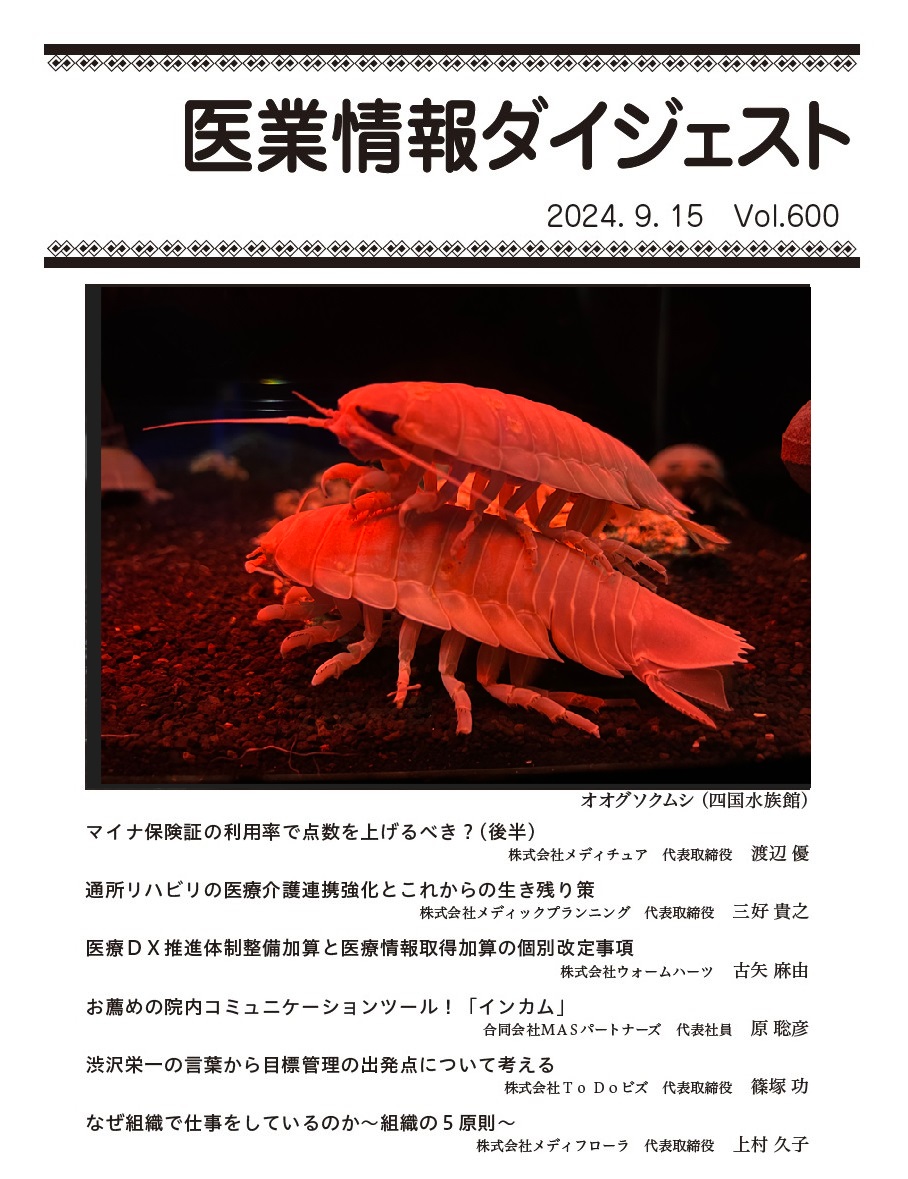
健康診断の受診者が増えてくる秋がもう直前まで迫ってきていますね。健康に過ごすために毎日の食生活や運動を意識するように、組織が健康に存続していくためにも必要な要素があります。しかし、 「組織で仕事をすること」 が当たり前の環境にある医療機関の場合、改めてその要素に思いを馳せる機会は多くないようです。今回は 「組織の5原則」 と呼ばれる、組織が健全に機能するための要素を学んだ医療機関のリーダーの気付きをご紹介いたします。
ケース:
日本海側に面する県にあるクリニックのA院長のお話です。A院長は先代であるご両親が開院したクリニックを継ぎ、院長に就任しました。先代院長である父しか組織のリーダーを知らないA院長は 「自分の組織作りが正しいのかどうか分からない」 と悩んでおり、筆者に相談がありました。
A院長は先代院長である父親が行っていた独裁的な院長の姿に不満を持っていました。A院長は自分の代ではスタッフ自身が自ら考え、良いと思うことを提案することができ、そして改善に向けた行動を自分たちで選択できる組織作りが良いと思い、A院長以外は全てフラットな、階層のない組織体制に変化させたのでした。
A院長 「先日も長く勤めていた看護師さんが退職の意を示したのです。退職理由は本人曰く 『一身上の都合』 とのことでしたが、他のスタッフが 『人間関係のトラブルらしい』 『院長に不満があるようだ』 と話していることを知りました。私は自分が院長として相応しいのか分からなくなってきてしまって……。何から勉強すれば良いのでしょうか?」
筆者 「組織の5原則というのは知っていますか? 組織運営を行うに当たり、頭に入れておいた方が上手く物事が進みやすい原則があるのです」
A院長は先代院長である父親が行っていた独裁的な院長の姿に不満を持っていました。A院長は自分の代ではスタッフ自身が自ら考え、良いと思うことを提案することができ、そして改善に向けた行動を自分たちで選択できる組織作りが良いと思い、A院長以外は全てフラットな、階層のない組織体制に変化させたのでした。
A院長 「先日も長く勤めていた看護師さんが退職の意を示したのです。退職理由は本人曰く 『一身上の都合』 とのことでしたが、他のスタッフが 『人間関係のトラブルらしい』 『院長に不満があるようだ』 と話していることを知りました。私は自分が院長として相応しいのか分からなくなってきてしまって……。何から勉強すれば良いのでしょうか?」
筆者 「組織の5原則というのは知っていますか? 組織運営を行うに当たり、頭に入れておいた方が上手く物事が進みやすい原則があるのです」
【組織の⑤原則】※ 解説者により表現には様々ありますが基本的な概念は同じです
1.指示・命令一元化の原則:
命令系統は1本が原則! 複数の命令系統は業務の混乱を招く
2.統制範囲の原則(スパン・オブ・コントロール):
直接監督する部下は適切な数がある
3.職務割当(分担)の原則:
部下同士の業務は不必要に重複させてはならない
4.権限委譲の原則(例外の法則):
責任のある業務にはそれに相当する権限が与えられなければならない
5.職務三面等価の原則(責任・権限一致の法則):
権限・責任・職務は等しく関係しあっている
A院長 「階層がなくフラットな組織にすることで、スタッフは緊張感から解放されて自由に発言ができ、行動ができるものと思っていました。よくスタッフから 『これはどうすれば良いですか?』 と聞かれても、 『自分たちで考えてくれれば良いよ』 と、口うるさくリーダーが色々と言うよりも良かれと思って伝えていましたが、スタッフたちに発言の自由は与えていても権限を与えていた訳ではありません。自由に発言して良いと伝えても、何をどこまでできるのか何も伝えていなければ、どう行動して良いか分からないですよね。私が尊敬する経営者が 『私はスタッフに何も伝えていないですよ』 と言っていたことを鵜呑みにしていましたが、肝心な組織が大切にする理念は常にスタッフに伝えていたことも思い出しました。組織における指示命令とは 『やれ!』 ではなく、思いを伝えることも指示命令なのですね。私の組織がなぜ上手く回っていないのか、考えるきかっけになりました」
少し考え込むとA院長は次のようにつぶやかれたのでした。
A院長 「これって世の中のリーダーは全員分かっているものなのですか?」
このケース、どのような感想を持ちましたか? この組織の5原則について、組織論を学ぶ上で目にした方も多いと思います。文面を読んでみると 「なるほど当然である」 とすんなり理解できると思いますが、いざ自分の組織を振り返ってみると相反する実態があることに気が付くリーダーが多いようです。
もちろん、あくまで 「原則」 であり、この原則通りでなくとも組織は問題なく機能することはあります。ただし、基本を知らずに組織改善に取り組もうとするとどこかで歪が生まれるものです。皆さまの組織はこの原則に立ち返るといかがでしょうか? より良い健全な組織運営のために、ぜひ職員の皆さまと原則について考える時間を取られることをお勧めいたします。
【2024. 9. 15 Vol.600 医業情報ダイジェスト】
命令系統は1本が原則! 複数の命令系統は業務の混乱を招く
2.統制範囲の原則(スパン・オブ・コントロール):
直接監督する部下は適切な数がある
3.職務割当(分担)の原則:
部下同士の業務は不必要に重複させてはならない
4.権限委譲の原則(例外の法則):
責任のある業務にはそれに相当する権限が与えられなければならない
5.職務三面等価の原則(責任・権限一致の法則):
権限・責任・職務は等しく関係しあっている
A院長 「階層がなくフラットな組織にすることで、スタッフは緊張感から解放されて自由に発言ができ、行動ができるものと思っていました。よくスタッフから 『これはどうすれば良いですか?』 と聞かれても、 『自分たちで考えてくれれば良いよ』 と、口うるさくリーダーが色々と言うよりも良かれと思って伝えていましたが、スタッフたちに発言の自由は与えていても権限を与えていた訳ではありません。自由に発言して良いと伝えても、何をどこまでできるのか何も伝えていなければ、どう行動して良いか分からないですよね。私が尊敬する経営者が 『私はスタッフに何も伝えていないですよ』 と言っていたことを鵜呑みにしていましたが、肝心な組織が大切にする理念は常にスタッフに伝えていたことも思い出しました。組織における指示命令とは 『やれ!』 ではなく、思いを伝えることも指示命令なのですね。私の組織がなぜ上手く回っていないのか、考えるきかっけになりました」
少し考え込むとA院長は次のようにつぶやかれたのでした。
A院長 「これって世の中のリーダーは全員分かっているものなのですか?」
このケース、どのような感想を持ちましたか? この組織の5原則について、組織論を学ぶ上で目にした方も多いと思います。文面を読んでみると 「なるほど当然である」 とすんなり理解できると思いますが、いざ自分の組織を振り返ってみると相反する実態があることに気が付くリーダーが多いようです。
もちろん、あくまで 「原則」 であり、この原則通りでなくとも組織は問題なく機能することはあります。ただし、基本を知らずに組織改善に取り組もうとするとどこかで歪が生まれるものです。皆さまの組織はこの原則に立ち返るといかがでしょうか? より良い健全な組織運営のために、ぜひ職員の皆さまと原則について考える時間を取られることをお勧めいたします。
【2024. 9. 15 Vol.600 医業情報ダイジェスト】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
2025-12-23
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-01-16現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2026-01-16
骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~
2026-01-15
地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-
2026-01-15
【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略
2026-01-14
敷地内薬局の評価の在り方の検討
2026-01-13
財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し
2026-01-09
現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記
2026-01-09
短期的に効率を重視するか、中長期的に個人が成長する環境をつくるか
2026-01-09
長時間労働の是正と時間外労働の事前申請
2026-01-09
患者に “選ばれるクリニック” はこうつくる!
2026-01-08
「療養・就労両立支援指導料」について運用の留意点
2026-01-07
中山間・人口減少地域での新しい特例介護サービス案
2026-01-06
精神病床から介護医療院の道を整備すべき

