組織・人材育成
ティーチング?コーチング? 学べる環境を作るために考えたいこと
組織力が高まるケーススタディ
株式会社メディフローラ 代表取締役 上村 久子
近頃、大変ありがたいことに、チーム作りやリーダー育成についての研修をさせていただく機会が増え、その中で 「育成に悩んでいる」 という相談をいただくことが増えています。色々な世代が集まる組織の中で、特に自分とは異なる世代に対する育成にまつわるお悩みは尽きることがなく、様々な観点からご質問をいただいております。
今回は、いただいたご質問の中で質問者が気付いた 「学べる環境作りのヒント」 について学んでいきたいと思います。
今回は、いただいたご質問の中で質問者が気付いた 「学べる環境作りのヒント」 について学んでいきたいと思います。
ケース
ある公開研修終了後、中国地方のクリニックに勤める若手リーダーAさんが神妙な面持ちで筆者のもとにやってきました。この研修は 「現代における組織づくりとリーダーの役割」 を題材にしたもので、Aさんは今の自分の組織の課題を解決する方法を知りたいと参加されたのでした。
Aさん 「実は育成で悩んでいます。新人育成でティーチングとコーチングはいつ切り替えるべきですか?色々な講師に聞いているのですが、納得いかなくて……」
筆者 「ご質問ありがとうございます。色々な言葉の解説がありますが、簡単に説明するならば、ティーチングは知識や技術を伝えること、コーチングは気づきや答えを導くことと私は表現します。ただ、実際の育成ではティーチングだけ、コーチングだけ、と明確に分けて行うことは現実的ではないと私は考えています」
Aさん 「なるほど、そう言われてみると、知っておく必要がある知識や技術は際限がありませんし、教育の初期段階であっても学びを定着させていくためには気づきが必要ですものね」
筆者 「おっしゃる通りだと思います。育成におけるティーチングとコーチングの関係は以下の図のイメージだと私は考えています」
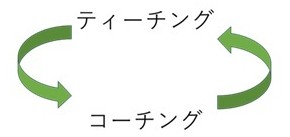
筆者 「特に私が重要だと思うのは、育成者が望む育成の成果を得るためには、【忘れる】など、記憶の定着のために教えられる側の脳内に起こる何らかの過程が重要だということです。ある試験を合格するために知識を詰込むことが仕事における育成ではなく、必要な知識や技術を中長期的に定着させ、応用させていくスキルを磨くことが仕事における育成のはずです。そのため、育成者がいかに必要な情報について上手に説明したとしても、それを受け止める教えられる側の工夫も必要になります。つまり、昨今は教えられる側にとって “教えられ方” の学びも必要ではないかと考えているのです。仕事における教えられ方について、学習の機会を持ったことはありますか?」
Aさん 「確かに……私は育成者が上手に教えることができたら、後は教えられる側が自分で身に付くように努力すべきであると考えていました。思い返してみると、教えられる側が自分でできていると思っているが、私たち育成者からすると全くできていないという事象が最近増えているのです。それって、育成者が思うゴールと教えられる側が良しとするゴールが異なっているということですよね」
筆者 「学生時代の延長で教えられる側が受け身であると、教えられた文言をただ覚えることで良しとしてしまうことは十分に考えられます。仕事において学ぶとはどういうことか、どのような視点で教えられた内容を受け取り、自分のものにしていけば良いのか、例を挙げながら【教えられること】について学ぶ機会を作ってはいかがでしょうか?」
この話のあと、しばらくしてからAさんから連絡がありました。
Aさん 「半信半疑で教えられることについてのミーティングを行いました。その結果、これまで教えられる側がメモを取らないことや質問をしないことにモヤモヤしていましたが、教えられる側から 『これまで言えなかったけど、何を期待されているのかイマイチ分からなかったが、自分が知識を身につけて道具として使うことを期待されているのだということが少しわかった』 という言葉がありました。まだまだ道半ばですが、チーム一丸となって学べる環境を作れるように努めたいと思います」
このケース、どのような感想を持ちましたか?この連載でも何度か育成に関する悩みを吐露するリーダーの話を取り上げてきましたが、育成とは教える側と教えられる側の2者のコミュニケーションで行われるものである以上、より良い育成のためにはお互いを思い込みで理解するのではなく、知り合う努力が必要だと考えます。最近は育成者が教えられる側にとても気を遣って、言葉を選び、分かりやすく伝える工夫をしている場面に出会うことが多いのですが、その反面、教えられる側に対する教えられ方へのアプローチが少ないと感じます。ただ単に 「メモを取りなさい」 ではなく、個人個人で知識や技術が身に付く過程は異なるわけですから、 「あなたはどうしたら知識や技術を身に付けることができるのか色々な方法を試してみましょう」 と、自分の育成方法を考えさせる声掛けが必要なのではないかと思います。
難しいテーマですよね。このケースが少しでも皆さまの組織作りのお役に立てたならば幸いです。
【2025年9月1日号 Vol.9 メディカル・マネジメント】
Aさん 「実は育成で悩んでいます。新人育成でティーチングとコーチングはいつ切り替えるべきですか?色々な講師に聞いているのですが、納得いかなくて……」
筆者 「ご質問ありがとうございます。色々な言葉の解説がありますが、簡単に説明するならば、ティーチングは知識や技術を伝えること、コーチングは気づきや答えを導くことと私は表現します。ただ、実際の育成ではティーチングだけ、コーチングだけ、と明確に分けて行うことは現実的ではないと私は考えています」
Aさん 「なるほど、そう言われてみると、知っておく必要がある知識や技術は際限がありませんし、教育の初期段階であっても学びを定着させていくためには気づきが必要ですものね」
筆者 「おっしゃる通りだと思います。育成におけるティーチングとコーチングの関係は以下の図のイメージだと私は考えています」
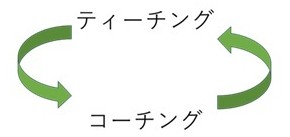
筆者 「特に私が重要だと思うのは、育成者が望む育成の成果を得るためには、【忘れる】など、記憶の定着のために教えられる側の脳内に起こる何らかの過程が重要だということです。ある試験を合格するために知識を詰込むことが仕事における育成ではなく、必要な知識や技術を中長期的に定着させ、応用させていくスキルを磨くことが仕事における育成のはずです。そのため、育成者がいかに必要な情報について上手に説明したとしても、それを受け止める教えられる側の工夫も必要になります。つまり、昨今は教えられる側にとって “教えられ方” の学びも必要ではないかと考えているのです。仕事における教えられ方について、学習の機会を持ったことはありますか?」
Aさん 「確かに……私は育成者が上手に教えることができたら、後は教えられる側が自分で身に付くように努力すべきであると考えていました。思い返してみると、教えられる側が自分でできていると思っているが、私たち育成者からすると全くできていないという事象が最近増えているのです。それって、育成者が思うゴールと教えられる側が良しとするゴールが異なっているということですよね」
筆者 「学生時代の延長で教えられる側が受け身であると、教えられた文言をただ覚えることで良しとしてしまうことは十分に考えられます。仕事において学ぶとはどういうことか、どのような視点で教えられた内容を受け取り、自分のものにしていけば良いのか、例を挙げながら【教えられること】について学ぶ機会を作ってはいかがでしょうか?」
この話のあと、しばらくしてからAさんから連絡がありました。
Aさん 「半信半疑で教えられることについてのミーティングを行いました。その結果、これまで教えられる側がメモを取らないことや質問をしないことにモヤモヤしていましたが、教えられる側から 『これまで言えなかったけど、何を期待されているのかイマイチ分からなかったが、自分が知識を身につけて道具として使うことを期待されているのだということが少しわかった』 という言葉がありました。まだまだ道半ばですが、チーム一丸となって学べる環境を作れるように努めたいと思います」
このケース、どのような感想を持ちましたか?この連載でも何度か育成に関する悩みを吐露するリーダーの話を取り上げてきましたが、育成とは教える側と教えられる側の2者のコミュニケーションで行われるものである以上、より良い育成のためにはお互いを思い込みで理解するのではなく、知り合う努力が必要だと考えます。最近は育成者が教えられる側にとても気を遣って、言葉を選び、分かりやすく伝える工夫をしている場面に出会うことが多いのですが、その反面、教えられる側に対する教えられ方へのアプローチが少ないと感じます。ただ単に 「メモを取りなさい」 ではなく、個人個人で知識や技術が身に付く過程は異なるわけですから、 「あなたはどうしたら知識や技術を身に付けることができるのか色々な方法を試してみましょう」 と、自分の育成方法を考えさせる声掛けが必要なのではないかと思います。
難しいテーマですよね。このケースが少しでも皆さまの組織作りのお役に立てたならば幸いです。
【2025年9月1日号 Vol.9 メディカル・マネジメント】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略
2026-01-14
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”
2026-02-24
新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む
2026-02-20
新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資
2026-02-20
元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―
2026-02-20
在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察
2026-02-18
病院職員の退職給付制度について考える(1)
2026-02-16
現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2026-02-11
外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―
2026-02-10
薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―
2026-02-09
最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金
2026-02-06
薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討
2026-02-05
話しがズレていく…

