組織・人材育成
令和7年の人事院勧告から給与改善の方向性とアルムナイ採用について考える
人事・労務 ここは知っておきたい
株式会社ToDoビズ 代表取締役 篠塚 功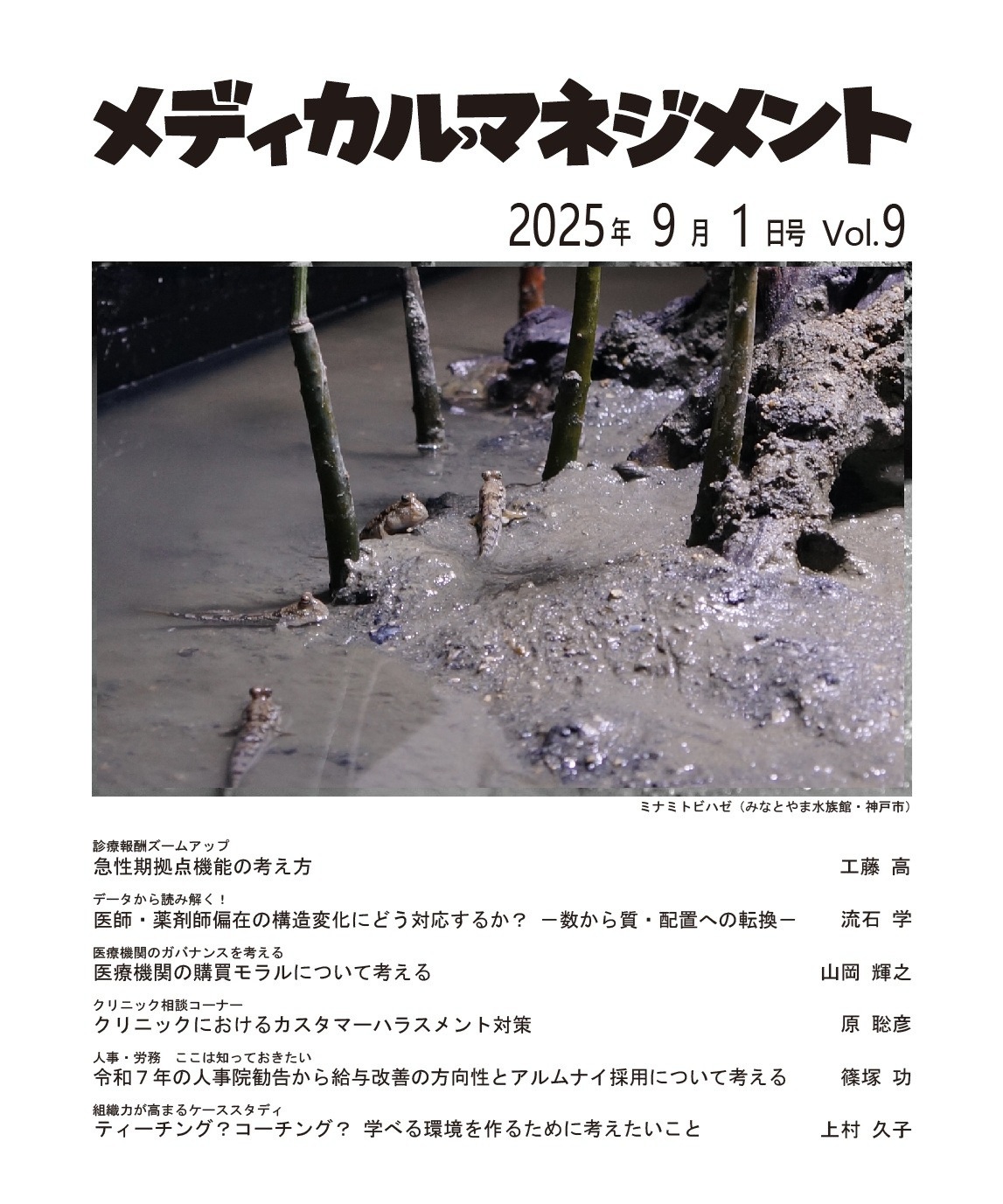
人事院は8月7日に、公務員人事管理と一般職の職員の給与について報告するとともに、令和7年の一般職の国家公務員の給与の改定について、国会と内閣に4年連続で給与の引き上げを勧告しました。人事院は、職員一人ひとりを大切な人的資本として捉え、その成長と挑戦を支えるための人材マネジメント改革にスピード感を持って取り組むとし、次の4つのポイント、 「①高い使命感とやりがいを持って働ける公務、②実力本位で活躍できる公務、③働きやすさと成長が両立する公務、④誰もが挑戦できる開かれた公務」 を柱としています。
これからの激しい人材獲得競争を勝ち抜くための改革ということであり、病院においても、参考にできることが多いと感じます。そこで今回は、給与勧告のポイントを確認し、病院の給与改善について考えるとともに、報告書の中から、病院こそ取り組むべきと思われるアルムナイ採用について考えます。
これからの激しい人材獲得競争を勝ち抜くための改革ということであり、病院においても、参考にできることが多いと感じます。そこで今回は、給与勧告のポイントを確認し、病院の給与改善について考えるとともに、報告書の中から、病院こそ取り組むべきと思われるアルムナイ採用について考えます。
令和7年給与勧告のポイントと給与改善の方向性
令和7年の給与勧告は、民間給与の状況を反映して、月給で3.62%(15,014円)引き上げることとしており、これはベースアップに該当しますが、これに定期昇給分を加えると、月給で約5.1%の給与改善とのことです。ちなみに、昨年はベースアップが2.76%、定期昇給分を加えると約4.4%の給与改善でしたので、さらに上回る改善となります。ベアが3%を超えるのは1991年以来です。
今年も昨年に続き、採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引き上げています。例えば、総合職(大卒)は242,000円(5.2%増の12,000円増)、一般職(大卒)232,000円(5.5%増の12,000円増)、一般職(高卒)200,300円(6.5%増の12,300円増)としています。さらに、本府省採用の総合職(大卒)は301,200円となり、初任給が30万円を超えています。また、昨年同様、若年層に重点を置いた改定であり、例えば、行政職俸給表(一)の平均改定率は、1級(係員)5.2%、2級(主任等)4.2%、全体で3.3%となっています。
なお、先述の実力本位で活躍できる公務を実現すべく、今後、給与体系を年功的なものから、職務・職責をより重視した新たな制度へと転換を図っていくこととし、まず令和7年度では、官民給与を比較する際の対象企業規模の引き上げ(企業規模50人以上から100人以上へ)、本府省の幹部・管理職員への手当の拡充、昇格に一定期間を求める仕組み(在級期間表)の廃止などを先行して行うとしています。例えば、本府省業務調整手当について、
幹部・管理職員を新たに支給対象に加え、51,800円を支給し、課長補佐級の手当額を10,000円引上げ、係長級以下の手当額を2,000円引き上げるとしています。
これらは、筆者が行う病院の人事制度改革の方向性と一致しています。すなわち、初任給および若い人材の給与を引上げ、重要な職責である管理職の給与も同時に引上げることを推奨しています。さらに、昇格要件としての在級年数についても、最近は、上位等級においては廃止、下位等級においては1~2年程度に短くするようにしています。
勧告は、賞与についても、昨年に続き引上げ、現在の4.6ケ月を4.65ケ月分とし、この引上げ分は期末手当及び勤勉手当に0.025ケ月分ずつ均等に配分するとしています。財源が限られている病院においては、採用力を強化するため、何とか若い人の給与を改善できたとしても、賞与の改善までは困難でしょう。なお、宿日直手当の改善や、地域別最低賃金の額を下回る場合の差額補填の手当等も勧告しており、参考にできると思われます。
今年も昨年に続き、採用市場での競争力向上のため、初任給を大幅に引き上げています。例えば、総合職(大卒)は242,000円(5.2%増の12,000円増)、一般職(大卒)232,000円(5.5%増の12,000円増)、一般職(高卒)200,300円(6.5%増の12,300円増)としています。さらに、本府省採用の総合職(大卒)は301,200円となり、初任給が30万円を超えています。また、昨年同様、若年層に重点を置いた改定であり、例えば、行政職俸給表(一)の平均改定率は、1級(係員)5.2%、2級(主任等)4.2%、全体で3.3%となっています。
なお、先述の実力本位で活躍できる公務を実現すべく、今後、給与体系を年功的なものから、職務・職責をより重視した新たな制度へと転換を図っていくこととし、まず令和7年度では、官民給与を比較する際の対象企業規模の引き上げ(企業規模50人以上から100人以上へ)、本府省の幹部・管理職員への手当の拡充、昇格に一定期間を求める仕組み(在級期間表)の廃止などを先行して行うとしています。例えば、本府省業務調整手当について、
幹部・管理職員を新たに支給対象に加え、51,800円を支給し、課長補佐級の手当額を10,000円引上げ、係長級以下の手当額を2,000円引き上げるとしています。
これらは、筆者が行う病院の人事制度改革の方向性と一致しています。すなわち、初任給および若い人材の給与を引上げ、重要な職責である管理職の給与も同時に引上げることを推奨しています。さらに、昇格要件としての在級年数についても、最近は、上位等級においては廃止、下位等級においては1~2年程度に短くするようにしています。
勧告は、賞与についても、昨年に続き引上げ、現在の4.6ケ月を4.65ケ月分とし、この引上げ分は期末手当及び勤勉手当に0.025ケ月分ずつ均等に配分するとしています。財源が限られている病院においては、採用力を強化するため、何とか若い人の給与を改善できたとしても、賞与の改善までは困難でしょう。なお、宿日直手当の改善や、地域別最低賃金の額を下回る場合の差額補填の手当等も勧告しており、参考にできると思われます。
アルムナイ採用の制度整備
報告の中に、最近注目されているアルムナイ採用を可能とする制度整備についても書かれていました。アルムナイ採用とは、一度退職した職員を再度職員として迎える制度です。アルムナイとは、卒業生や同窓生を意味する英語ですが、近年では人事領域で退職者を指す言葉として注目されています。筆者は、病院の人事課長をしていた30年前に、この仕組みを看護師や医師の採用において重視していました。例えば、循環器内科を目指す若い医師に、一旦自院を辞めて、循環器専門の病院で経験を積んでもらい、数年後に将来の幹部候補として戻ってもらうといったことをしていたわけです。また、看護師については、当時から不足していたこともあり、退職した看護師の名簿を整備し、再就職の声掛けを定期的に行っていました。当時は、アルムナイ採用という言葉はありませんでしたが、昔よりさらに人材不足の今日、病院においても、アルムナイ採用を行う制度を整備する必要性があると考えます。退職者をアルムナイ人材として登録し、定期的に情報を発信してネットワークを作り、さらに復職者の研修プログラムを整備し、復職時の処遇を優遇するなど、制度整備を進め、アルムナイ採用に力を入れることは、即戦力となる人材確保につながると期待します。
【2025年9月1日号 Vol.9 メディカル・マネジメント】
【2025年9月1日号 Vol.9 メディカル・マネジメント】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-26【セミナーのご案内】2026年度診療報酬改定を踏まえたリハビリ機能強化による病院の経営戦略
2026-01-14
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-02-25組織の成長を支える“日常の仕組みづくり”
2026-02-24
新年の初めに、医療従事者のウェルビーイングをともに育む
2026-02-20
新規開業で最も軽視される 「採用と研修」 という投資
2026-02-20
元気なうちに“バトンを渡す”という選択 ―地域医療の継続か、自院の幕引きか―
2026-02-20
在宅療養支援体制における薬剤師の実践的役割の一考察
2026-02-18
病院職員の退職給付制度について考える(1)
2026-02-16
現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2026-02-11
外来管理加算の見直しが問いかけるもの ―市場収縮期の医療経営は?―
2026-02-10
薬局はどこへ向かうのか ―財務省が示す 「次のモデル」 ―
2026-02-09
最低賃金引上げの影響と補正予算からの補助金
2026-02-06
薬局報酬、かかりつけ薬剤師制度の検討
2026-02-05
話しがズレていく…

