組織・人材育成
人事評価のフィードバックのポイント
上司・部下の認識パターンの違いとフィードバックの仕方
株式会社To Doビズ 代表取締役 篠塚 功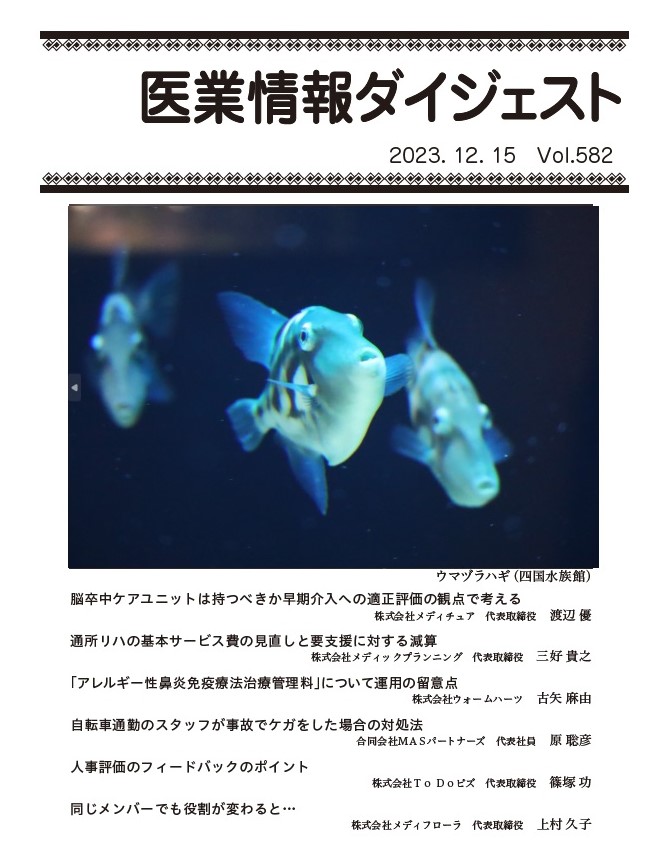
人事評価の育成面接の時期になると、研修会の依頼やメールでの質問が増えます。先日も「年上の部下への面接の仕方についてポイントを教えてほしい」という質問をいただきました。最近は、年功的な人事制度から、能力や成果主義の人事制度が主流となり、年上の部下を持つ人も増えましたので、このようなことを気にされる方もいると思います。ちなみに、この質問に対しては次のように返答しました。
「年齢等に関係なく、同じように接することが基本です。上司が上で部下が下ということではありませんから、誰に対しても相手を尊重して面接をします。昔の上司は部下を呼び捨てにするなど上下関係を示す傾向がありましたが、上司と部下の関係は、上下関係ではなく単に役割が異なるだけです」
人事評価の運用が上手くいき、職員が定着するか否かは、この育成面接にかかっていると言っても過言ではありません。人材マネジメントの基本は「個人への敬意」と「信頼」です。この2点を肝に命じて、面接をすることが大前提です。部下に敬意を示し、信頼する姿勢を持って面接に臨むべきでしょう。しかし、姿勢だけでは不安を払拭できませんから、今回は、育成面接の仕方について考えます。
「年齢等に関係なく、同じように接することが基本です。上司が上で部下が下ということではありませんから、誰に対しても相手を尊重して面接をします。昔の上司は部下を呼び捨てにするなど上下関係を示す傾向がありましたが、上司と部下の関係は、上下関係ではなく単に役割が異なるだけです」
人事評価の運用が上手くいき、職員が定着するか否かは、この育成面接にかかっていると言っても過言ではありません。人材マネジメントの基本は「個人への敬意」と「信頼」です。この2点を肝に命じて、面接をすることが大前提です。部下に敬意を示し、信頼する姿勢を持って面接に臨むべきでしょう。しかし、姿勢だけでは不安を払拭できませんから、今回は、育成面接の仕方について考えます。
未来に向かった話をする
育成面接は、部下の過去の職務行動を捉え評価し分析した結果をフィードバックするわけですから、結果が思わしくなかった部下にとっては苦痛でしょうし、一歩間違えればモチベーションを下げることにもなります。しかし、たとえいくつかの結果が思わしくなかったとしても、仕事への取り組み姿勢や、他のスタッフへの働きかけ、達成した目標など、ほめる点は必ずあるはずです。したがって、結果が思わしくなかった原因は「注意する点」として整理しておくとして、「ほめる点」も整理しておいて部下にはっきりと伝える必要があります。そして、注意する点は、だらだらと注意するのではなく、そのことが育成するポイントになるわけですから、どのようにして育成点を克服するかといった育成プランに切り替え、未来に向かった話に変えていく必要があります。
上司が、部下の育成のために、今後の能力開発目標のプランを考えて面接に臨むことにより、部下は過去から未来に向かって自らの成長を考えることができ、モチベーションを高めることができるのです。部下が、その組織に定着する上で、今までこの組織で成長できたという成長実感も大事ですが、それにも増して、これから未来に向かって、この上司の下であれば成長できそうだという成長予感を感じることこそ大事なことだと考えます。したがって、育成面接の大事なポイントは、だらだらと過去のことに触れるのではなく、未来に向かった話に切り替えることです。
上司が、部下の育成のために、今後の能力開発目標のプランを考えて面接に臨むことにより、部下は過去から未来に向かって自らの成長を考えることができ、モチベーションを高めることができるのです。部下が、その組織に定着する上で、今までこの組織で成長できたという成長実感も大事ですが、それにも増して、これから未来に向かって、この上司の下であれば成長できそうだという成長予感を感じることこそ大事なことだと考えます。したがって、育成面接の大事なポイントは、だらだらと過去のことに触れるのではなく、未来に向かった話に切り替えることです。
上司・部下の認識パターンの違いとフィードバックの仕方
最近の人事評価は、本人が評価対象期間をふりかえって、自らの職務行動や能力を評価する自己評価をさせることが一般的です。本人が自らの行動の特性等に気づき、課題がある場合には見直す機会になるわけですが、上司と部下とで認識に違いがあると面接の仕方にも注意が必要です。先日も、「上司評価が低く、自己評価が高い職員へは、どのようにフィードバックすべきか」という質問を頂戴しました。これに対しては次のように回答しました。
「部下の評価の根拠を確認したうえで、上司評価の根拠を説明してください。上司の期待と本人の行動が一致していないわけですから、このような評価の違いが起こらないよう、上司として取ってもらいたい行動について十分説明をしてください。そして、部下がそれについてどのように考えるかを聴いてみてください。理解してもらえればよいですが、理解してもらえない時には、部下に求める行動の根拠など十分に説明をするとともに、そのために身に付けてもらわなければならない能力等があれば、その能力の育成について一緒に考えることが大事なことです」
逆に、「上司評価が高く、部下評価が低い場合」には、「①高い評価を称賛する、②高評価を付けた事実を示して理由を伝える、③部下が不満足と感じる点を傾聴する、④上司としての評価理由・根拠を説明し励ます」といった手順でフィードバックします。次に「上司評価も部下評価も高い場合」には、「①高い評価を称賛する、②事実を示して理由を伝える、③現状に満足せずさらに高いレベルを目指していくように、期待を伝え動機づける」という手順で面接をします。最後に、「上司評価も部下評価も低い場合」には、「①部下が前向きに努力したことはほめる、②なぜ、上手くいかなかったかについて、具体的な行動をふり返る、③今回の経験を次の取り組みに活かすように伝え、期待の言葉をかける」といったフィードバックをしてはどうかと考えます。
【2023. 12. 15 Vol.582 医業情報ダイジェスト】
「部下の評価の根拠を確認したうえで、上司評価の根拠を説明してください。上司の期待と本人の行動が一致していないわけですから、このような評価の違いが起こらないよう、上司として取ってもらいたい行動について十分説明をしてください。そして、部下がそれについてどのように考えるかを聴いてみてください。理解してもらえればよいですが、理解してもらえない時には、部下に求める行動の根拠など十分に説明をするとともに、そのために身に付けてもらわなければならない能力等があれば、その能力の育成について一緒に考えることが大事なことです」
逆に、「上司評価が高く、部下評価が低い場合」には、「①高い評価を称賛する、②高評価を付けた事実を示して理由を伝える、③部下が不満足と感じる点を傾聴する、④上司としての評価理由・根拠を説明し励ます」といった手順でフィードバックします。次に「上司評価も部下評価も高い場合」には、「①高い評価を称賛する、②事実を示して理由を伝える、③現状に満足せずさらに高いレベルを目指していくように、期待を伝え動機づける」という手順で面接をします。最後に、「上司評価も部下評価も低い場合」には、「①部下が前向きに努力したことはほめる、②なぜ、上手くいかなかったかについて、具体的な行動をふり返る、③今回の経験を次の取り組みに活かすように伝え、期待の言葉をかける」といったフィードバックをしてはどうかと考えます。
【2023. 12. 15 Vol.582 医業情報ダイジェスト】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2026-01-14【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 これからの薬局経営の方向性と戦略
2025-12-24
【セミナーのご案内】日総研主催「重症度、医療・看護必要度 「新基準」への対応と看護マネジメント」
2025-12-23
【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』
お知らせ一覧
[新着記事]
2026-01-22外注契約の落とし穴 ―契約を結ぶ前に考えておきたいこと―
2026-01-21
「辞めます」と言われてからでは遅い! ―院長のマネジメント力アップのポイント―
2026-01-20
医療的ケア児と地域をつなぐ ~小児在宅と薬剤師の関わり~
2026-01-19
病院建設を進める際の問題点について考える(2)
2026-01-16
現役薬剤師・葦立ひとみの☆ななころびやおき☆
2026-01-16
骨太方針2025から見える薬局の経営変化 ~OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し~
2026-01-15
地域包括ケア病棟のジレンマ -地域包括医療病棟導入後の 「居場所」 をどう設計するか-
2026-01-15
【セミナーのご案内】令和8年度薬価・調剤報酬改定を読み解く これからの薬局経営の方向性と戦略
2026-01-14
敷地内薬局の評価の在り方の検討
2026-01-13
財務省の意向で、かかりつけ医関連点数は見直し
2026-01-09
現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記
2026-01-09
短期的に効率を重視するか、中長期的に個人が成長する環境をつくるか

