組織・人材育成
人事評価委員会の設置と活動内容、運営のポイント
人事・賃金制度の導入と適切な運用
株式会社To Doビズ 代表取締役 篠塚 功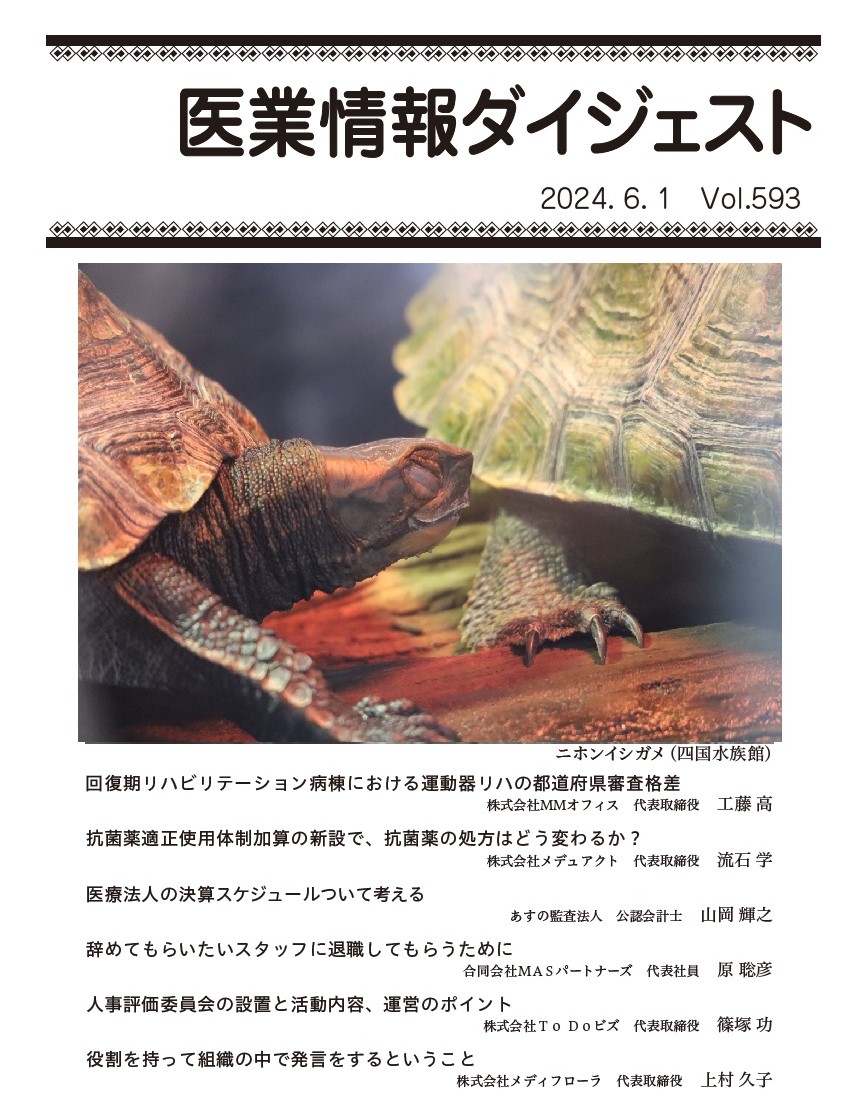
新年度に入り、数病院と人事・賃金制度の運用支援の契約を交わしました。支援の内容は、病院によって様々ですが、主なものは、人事評価委員会の運営や人事評価の研修になります。
人事・賃金制度を適切に運用するためには、人事評価委員会を設置し、委員会が中心となって、年間の事業計画を立て実行していく必要があります。そこで今回は、人事評価委員会の設置と活動内容、運営のポイントについて考えます。
人事・賃金制度を適切に運用するためには、人事評価委員会を設置し、委員会が中心となって、年間の事業計画を立て実行していく必要があります。そこで今回は、人事評価委員会の設置と活動内容、運営のポイントについて考えます。
人事評価委員会の設置と主な活動内容
人事・賃金制度の運用を行う部門は人事部になりますが、病院においては人事部が存在しない所も多く、人事評価制度や、評価結果を反映させる賃金制度を導入しても、上手く運用が継続できないのが実際ではないかと危惧します。そこで、これを継続するために、人事評価委員会や人事・賃金制度委員会を設置することを推奨しています。
人事評価委員会で活動すべき項目は、次の事項が考えられます。
人事評価委員会で活動すべき項目は、次の事項が考えられます。
- 人事・賃金制度の職員への周知
- 人事評価結果の判定や結果の調整等の検討
- 評価者研修、被評価者研修の開催
- 人事・賃金制度に関する職員の意識調査の実施
- 人事評価制度、賃金制度、等級制度の見直しに関すること などです。
人事・賃金制度を導入したら、賃金に関しては、原則として新しい賃金規程に則って人事担当者が運用をすればよいのですが、人事評価制度については、評価者と被評価者に制度の目的や運用方法を理解してもらい、運用してもらう必要があります。したがって、この委員会の活動は、主として人事評価制度の運用に関することが中心になりますので、人事評価委員会という名称とする所が多いですが、所管する範囲は人事・賃金制度全体にしておくとよいでしょう。
すなわち、主な委員会活動は、各部署で目標管理や人事評価が適切に行われているかなど評価結果の確認と、適切に行うためにどのような研修等を行うかを検討することになるわけです。例えば、当初決めた評価判定基準通りに運用した場合に、ほとんどの職員がS~Dの評価段階でC評価となってしまったのでは、職員のモチベーションを下げるだけで、何のために人事評価を行ったのか分からなくなります。その場合、導入当初は判定基準の見直しが必要になるかもしれません。あるいは、部門間で評価にかなりのばらつきがある場合には、評価結果を調整するか否かの判断等も必要となるでしょう。人事評価制度においても、賃金制度と同様、原則としては、当初決めたルールに則って運用するのが理想ですが、導入当初は経過措置として、委員会を中心に様々な判断をする必要が生じます。今までの経験から、このことをおろそかにして単純に当初決めた通りに運用するだけでは、人事評価制度を上手く組織に定着させることは難しいと感じています。
また、人事・賃金制度を導入して定着したら、制度に関する職員の意識調査を行い、定期的に見直しを検討する必要もあるでしょう。若い労働力の確保が難しくなっている今日、人事評価や賃金等の処遇に関することは、人事担当者だけが注意を払うのではなく、委員会として、常に注意し見直しや管理職への指導を行う必要があると考えます。
すなわち、職員の不満や課題はできるだけ早く察知し対応をしなければ、人材の定着を図ることは、ますます難しくなるのではないでしょうか。
人事評価委員会を設置し、年間の事業計画を立て評価判定会議の実施等先述の活動を行うことで、職員の育成や処遇に関して組織的に検討することとなり、管理職の育成や職員の定着につながり、組織を活性化するものと考えます。
人事評価委員会等運営のポイント
人事評価委員会を運営する中心は、人事部と委員会の委員長になりますが、委員長の選出は、事務部長とか人事部長という事務職に限らず、看護部長とか医療技術部長などから行うことも必要です。組織全体に人事評価制度を定着させるためには、各部門のトップに関心を持ってもらう必要があるからです。また、委員会にオブザーバーとして外部の人間を入れることで、ある部門に有利になるようなことがなく、さらには、一般的な人事・賃金制度の運用を踏まえた判断をしてもらえることが期
待できます。
今まで、人事・賃金制度を導入していなかった病院においては、導入して数年は、人事評価結果を点数に置き換える作業や職員の意識調査のアンケートの集計、研修会の開催など、人事部の業務が増大します。人事評価システムを入れることも一方策ですが、システム構築や維持費にかなりの費用を要することから、当面は、手前味噌ではありますが、筆者のような外部の人間に、1年に数回支援をしてもらうことで、これらの作業を削減するとよいと考えます。委員会運営に力を注ぐためにも、人事・賃金制度の運用の一部をアウトソーシングされるとよいでしょう。
【2024. 6. 1 Vol.593 医業情報ダイジェスト】
待できます。
今まで、人事・賃金制度を導入していなかった病院においては、導入して数年は、人事評価結果を点数に置き換える作業や職員の意識調査のアンケートの集計、研修会の開催など、人事部の業務が増大します。人事評価システムを入れることも一方策ですが、システム構築や維持費にかなりの費用を要することから、当面は、手前味噌ではありますが、筆者のような外部の人間に、1年に数回支援をしてもらうことで、これらの作業を削減するとよいと考えます。委員会運営に力を注ぐためにも、人事・賃金制度の運用の一部をアウトソーシングされるとよいでしょう。
【2024. 6. 1 Vol.593 医業情報ダイジェスト】
同カテゴリーの記事:

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20

2023-11-20
[事務れんらクンの更新情報]
2025-11-02「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.17)(令和7年10月1日事務連絡)」を追加しました
2025-10-22
「疑義解釈資料の送付について(その30)」を追加しました
2025-10-01
「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を追加しました
[お知らせ]
2025-12-23【セミナーのご案内】新社会システム総合研究所主催 『機能別病床管理・入退院支援のための制度理解と多職種連携 』
2025-11-22
【新刊のご案内】『病院薬剤師のための生成AI完全実践ガイド』
2025-10-10
【新刊のご案内】『コンサルタントご一行、病院経営を往く-エビデンスに基づく診療報酬の旅-』
お知らせ一覧
[新着記事]
2025-12-23【セミナーのご案内】
2025-12-23
令和8年度調剤報酬改定を考える
2025-12-22
正常分娩費用の自己負担無償化議論
2025-12-19
現役看護師・ヤマブキNsのおつかれさま日記
2025-12-19
私は職員のことを一番考えている
2025-12-19
今年の春闘の結果と病院の処遇改善への姿勢
2025-12-18
事例に学ぶ外来データ提出加算導入の極意!
2025-12-17
在宅療養指導管理材料加算について運用の留意点
2025-12-16
介護人材採用のカギはネット広告一択
2025-12-15
急速な環境変化に精神科病院は地域移行を目指せるのか
2025-12-12
生成AIとの付き合い方
2025-12-11
リテンションとしての新たなポジションの創設

